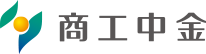輝く地域の中小企業
老舗味噌蔵の醸造技術で
発酵利用の健康食品を開発
会津天宝醸造株式会社

「玄米を糀に」の発想から「玄米甘酒」誕生
会津の気候、風土、歴史に育まれ150年

会津地方は福島県西部、越後山脈と奥羽山脈に挟まれた盆地にある。透水性の高い砂礫層が土地を覆い、多くの川は伏流水となって地下を流れる。この砂礫層が天然の濾過器となって良質の地下水が豊富で、これを利用した味噌造りが約300年前、江戸中期から発達した。
会津天宝醸造(株)(会津若松市、満田盛護社長)は、江戸末期から塩の販売や味噌の製造小売を手がけていた初代満田善内氏が1871年、廃藩置県で若松県(現在の会津地方および新潟県東蒲原郡)ができたとき、県生産局より味噌の製造販売の鑑札を受け創業した。
醸造技術を生かし、1923年に醤油製造を開始し、東京進出を図ったが、昭和恐慌に遭遇し一時撤退した。1928年には、会津の農作物を生かした味噌漬けなど漬物製造にも進出。戦後の1961年、天寶醸造(株)として株式会社化するとともに量産体制を整え、翌年現社名 に改称した。会津の名を冠し、地元に根差した醸造メーカーとして発展し、会津味噌を中心に幅広く発酵食品の製造を手がけている。
研究機関、大学と連携し新しい健康食品を開発

「お客様の健康第一」をモットーに天然素材原料にこだわり、味噌、醤油醸造および漬物製造を基幹事業として発展した。その結果、大手コンビニのプライベート・ブランドを受託するなど、幅広い顧客層からの信頼を得てきた。
観光関連では、尾瀬国立公園の玄関口に当たる檜枝岐村に伝わる伝統食品である「岩魚味噌」を商品化した。尾瀬の清流で育つ岩魚をまるごと焼きほぐした身を味噌にまぜたもので、2011年、第52回全国推奨観光土産品審査会で農林水産大臣賞を受賞した。
味噌、醤油、漬物以外の発酵食品でも製品展開を進めており、糀をつかった甘酒、ドレッシングなどの生産にも進出している。
また「糀を大量につくる保有施設を活用し、新たな糀関連商品の展開を図ろうと新商品開発を進めた。商品化に成功した一例が『玄米オリザーノあまざけ』だ。震災復興支援事業の産学連携コーディネートにより実現した。琉球大学医学部第二内科の益崎裕章教授は、玄米が含むγ‐オリザノールという物質を研究し、玄米が健康長寿の鍵だと解明した。当社は福島県ハイテクプラザの指導のもと、玄米糀づくりを成功させ、商品化できた」と満田社長は振り返る。
会津の地で創業し、会津の地で発展
消費者に喜ばれる食品造り食品加工を通じ社会に奉仕

「奈良時代から日本人の健康と食卓を支えてきたといわれる伝統食材・味噌を今後も守り続けたい。味噌にとどまらず、食卓を楽しく豊かにする商品を開発し続けたい。それを通じて健康貢献、社会貢献の取り組みを続けたい。特に、道半ばの震災からの復興、観光の活性化に寄与したい」と満田社長は語る。
企業名:会津天宝醸造株式会社 スライド
企業データ
- 本社:福島県会津若松市大町1-1-24
- HP:https://www.aizu-tenpo.co.jp/
- TEL:0242-23-1616
- 創業:1871年
- 設立:1961年12月
- 資本金:8500万円
- 年商:20億円(2022年12月期)
- 従業員:95名(2023年1月)
商工中金は中小企業の価値向上に取組み、地域経済の活性化に貢献してまいります。まずは、ご相談ください。
お近くの各営業店までお電話ください。
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝祭日・12/31を除く)